「大げさだなあ」
憤怒の表情でウランドの腕を引っ張る秘書の背中を見ながら、殴られた本人は蚊に喰われた程度にしか考えていなかった。
それよりもスペードのキングのあの尖り具合を何とかしなければ、考えを支配していたのはその事ばかり。それくらい、ウランド本人にとっては殴られたことなど大したことはなかった。文字通り、"周囲をよそに"だった。
だが、今度は自身の上司に悩まされることになった。
◆
会議室につくなりその場の全員が、ウランドの腫れた頬に目を見張った。中でも直ぐ様、真っ直ぐと寄ってきたのはハートのキングだった。その怒りに震えるのを押し殺そうとした目に、今度はこっちに(会議に遅刻したため)殴られるのか、などと考えていた。
ところがその白魚のような細い指はそっとウランドの頬に触れると柔らかな光を放った。"治癒魔法"だった。その優しい手の感触とは反対に、漆黒の瞳に宿る光は冷徹だった。
「スペードのキングにやられたのか」
直感的に、是と答えるのはマズイ気がした。
「いいえ、ちょっと大きめの蚊に喰われただけです」
あまりに馬鹿げたその回答に、ハートのエースは殴られたことで不機嫌で、それをキングに当たっていると周囲は受け取った。
「お前は上司である私に虚偽の報告をするのか?」
「お言葉ですが、キング、私個人のプライベートです」
「勤務時間中にプライベート?」
「じゃあ時間休で」
「ガキか貴様は!」
その通りだと、周囲は呆れ返っていた。前ハートのキングが割といい加減な性格だったため、なあなあで流されていた部分が、このキングではそうはいかない。それを以前のいい加減な感じで済まそうとするウランドとは、こういった場面でウマが合うはずがなかった。
「何を気にされているのか理解に苦しみます。もしこの"蚊に刺され"が貴女の想像通りだったとして、どうされるおつもりですか? ただでさえ、今回の人事でトランプ全体が混乱しているのに、さらにそれを引っかき回すおつもりですか」
なるほど、とぼけた回答の意図は更に余計な混乱を招かないためか、場の全員が理解を示したように見えた。一人を除いて。
「金輪際スペードのキングに関わるな」
それは吐き捨てるような、口振りだった。
◆
「もしかしてさあ、スペードのキングとうちのキングって仲悪いの?」
秘書課の休憩室。各軍の秘書たちが集まるその秘密の園は軍を跨いだ人間関係の噂の宝庫だった。そこに現れた珍客に、秘書たちはお茶出し、椅子出し、茶菓子出しの大慌てだった。
「ハートのエース……初日からまたなぜそんな……」
「何か情報ない? このままじゃ仕事に支障がでかねない」
この化粧品の香りに満ち満ちた部屋に足を踏み入れるのは罪悪感というか申し訳なさというか恥ずかしさのようなものがあるが、最早それどころではなかった。たった半日だが、このままではトランプという組織自体が立ち行かなくなるのではないかという不安がこの禁断の地(秘書の休憩室)へと足を向けさせた。
「ご存知ないのですか? かなり有名ですけど」
「なんで?」
その当然のように出てくるべき質問に、答えられる者はいなかった。仲が悪いのは有名な話。だがその有名な噂には原因に関する情報は付随していなかった。
だがこのばつの悪い空気でエースを追い出す訳にもいかないと、ふくよかで気品のある年配の秘書課長が再度声をかけた。
「誰か何か知らない?」
「あの……」
プラチナブロンドに怯えたような澄んだ青い瞳、まるで妖精のような美しい女性。武骨なスペードのキングとは無縁そうだなというのが第一印象だった。
「お疲れ様です、ハートのエース。スペード軍第七秘書官リシュリュー・ラプンツォッドです」
「ご苦労様です、リシュリュー秘書官。何かご存知ですか?」
「お席を外しませんか?」
その様子に、"ビンゴ"と直感した。
◆
何やら秘密にしたそうな話をするのに選択したのは屋根の上だった。
「ここなら誰にも聞かれないでしょう」
そこまで気を使ってくれたのかとどこかホッとした様子で、リシュリューは腰を下ろした。
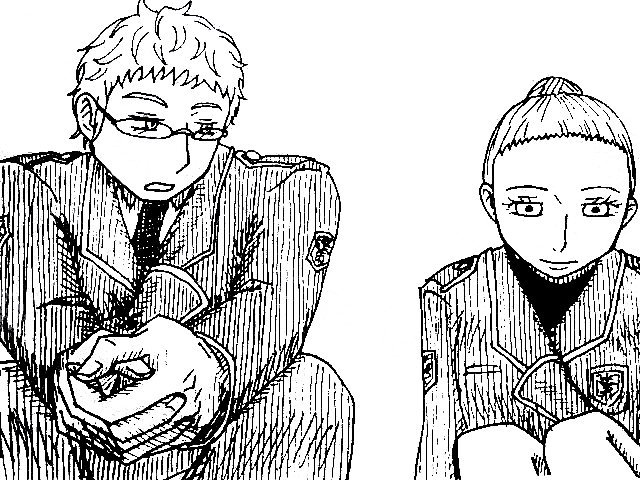
「スペードのキングはとても几帳面で思慮深く、不器用な方です」
「あー……なんか神経質な感じはしますねえ」
ちらりと青い瞳はウランドの頬の様子を窺った。
「殴られたとうかがいました」
すでに完治した左頬を掻きながらウランドは笑った。
「ああ、あんないきなり殴られたのは久しぶりです、面白かった」
「え……面白……?」
「ああ、で、なぜ殴られたかですが、なぜか話の文脈に全く出てきていない"ハートのキング"を引き合いに"比較しただろう"と。キングの地位であるのに隣の芝生に躍起になられてはトランプが上手く機能しません。別に仲良くならなくて構わないので、せめて仕事が回るようにしてほしい、それだけです」
そうして視線を向けた先の"妖精"はぽかんとウランドを見つめていた。
「……もしかしておかしなことをいいましたか?」
「いいえ、ハートのエース。貴方は正しい……スペードのキングは本当は心の親切な方です。朝の朝礼を鍛練の時間に置いたのも、業務に忙殺されている隊員たちが怪我をしないように、なるべく学生時代の運動量を、とのご意向かと」
あまりにこじつけに近いフォローかと、リシュリュー自身思ったが、ウランドは素直に真に受けたようだった。
「なるほど、それは周囲に伝わっていませんね。成果が出ればよいのでしょうが、このままでは周囲の心が離れるほうが早い。まず初めに集団の納得が必要でしょう」
困ったように、"妖精"の眉根が寄った。
「……貴方であれば、叶うでしょう。ですが、彼には"壁"がもう一枚あるのです。そのため、周囲から認められるには成果を出すことが近道だと考えておいでなんです」
――その壁とは、ジパング人であるということ
「うちのキングも同じですが」
「……カグヤさんとは置かれた環境が違いすぎました。どれだけ努力しても、ジパング人だからと。目に見える結果を残すしかなかったんです」
「やれやれ、未だに学生気分ということですか。困りました」
その痛烈な言葉にリシュリューは驚いた様子でウランドを見上げた。
「確かに結果は大事ですが、これはチームでの仕事です。成果を出せば単位をもらえて卒業(ゴール)ではありません。その先も、多くのヤマを仲間と乗り越えていかなければなりません。できないのであれば、そもそもトランプには向いていないと思います。……聞こえましたか、スペードのキング」
ぎょっとして、リシュリューは慌てて周囲を見渡した。
三角屋根の、丁度反対側。頭をさすりながらむくりと体を起こした、熊のような大男はギラリとウランドを睨み付けた。
「すみませんね、リシュリュー秘書官、ここに来たときにすでにスペードのキングがいらっしゃったのですが、まあちょうど良いかと」
リシュリューの顔には明らかに動揺が拡がっていた。
「トウジロウ、落ち着いて、これ以上内部で暴力なんて振るってクビにでもなったら、あなたマリア先生になんて顔向けするの……」
「どっちが早いか言うたなオッサン」
漆黒の鷹のような鋭い瞳とメガネの奥がぶつかった。
「みとれ、ホンマにどっちが早いか」
ウランドはやれやれとため息をついた。
「威勢の良い若獅子ですね、じゃあ見ててあげますからハート軍に迷惑だけはかけないでくださいね」
その後、確実に着々と、スペード軍はこれまで以上の事件解決率を誇った。だが、それに反比例するように、隊員たちは肉体的に、精神的に、疲弊していった。
そして今から二年前、"スペードのキング"トウジロウは再び事件を起こした。
――― A. ( スペードのキング降格事件3 ) ―――
2012.10.26 KurimCoroque(栗ムコロッケ)